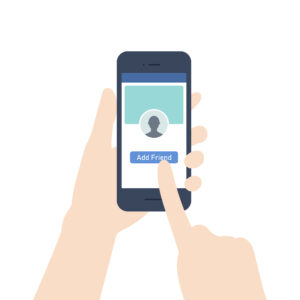新規事業やサービスを開始するにあたり、ホームページの作成を検討している方もいるでしょう。
ひとえにホームページといっても多種多様なサイト構成、デザインなどがあり、見やすいホームページにするためには「サイト構成」が欠かせません。サイト構成とは、ホームページの設計図にあたるものであり、作り込まれているかどうかで仕上がりに大きく影響します。
そこで今回は、ホームページのサイト構成とは何か、作り方やポイントなどを解説します。初心者の方にもわかりやすい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
サイト構成とは?
ホームページ制作におけるサイト構成とは、どこにどのような情報があるのか、カテゴライズした表のことです。
企業のホームページをイメージすると、「会社について」というボタンがあり、それをクリックすると「会社概要」「企業理念」「社長メッセージ」といったコンテンツが並ぶ仕様になっているものが多いでしょう。
一見、さまざまなコンテンツが並んでいるように思えるホームページですが、制作前の段階でサイト構成作り、どのコンテンツがどこにあるのかマップのようにわかりやすく振り分けられています。
仮にサイト構成がないままホームページ制作を進めてしまうと、設計図がないまま家を建てているような状態になり、中途半端で見にくいサイトになりかねません。後から修正するのには追加費用が発生するのが一般的であるため、余計なコストもかかるでしょう。
一方、サイト構成が作り込まれていれば、サイト構成をベースに制作できるので、スムーズに作成できるうえに高い完成度が期待できます。このように、サイト構成は良質なホームページを完成させるために、必要不可欠なものであるといえるでしょう。
【全4ステップ】サイト構成の作り方

では、具体的な作り方を見ていきましょう。
4つのステップがあり、順に進めていくことで基本的なサイト構成を作れます。自社サイトに置き換えて検討してみてください。
ステップ1:サイトの目的を決める
まずは、何を目的にサイトを作るのかを明確にしましょう。
ホームページから商品を売りたいのか、問い合わせ件数を増やしたいのかなど、目的によって必要な構成が変わります。
ステップ2:必要なページを書き出す
目的が決まったら、サイトに必要な情報を書き出してみましょう。
企業のホームページを作ると仮定して、必要なコンテンツを紹介します。
- 企業概要
- 企業理念
- 社長メッセージ
- 事業計画
- 事業内容
- 強み
- 先輩社員のメッセージ
- 社員の一日
- 職場環境
- 募集要項
- 採用スケジュール
- 問い合わせフォーム
どのようなコンテンツが必要か思い浮かばないときは、競合他社のサイトを参考にするとよいでしょう。また、必要なコンテンツをピックアップする段階であるため、分類などを気にする必要はありません。
ステップ3:書き出したページをカテゴリごとに整理する
必要なコンテンツのピックアップが終わったら、カテゴリごとに分類していきましょう。
先ほどピックアップしたコンテンツを例に分類してみました。
| 企業情報 | 事業情報 | 社員について | 採用情報 |
| ・企業概要 ・企業理念 ・社長・メッセージ ・事業計画 | ・強み ・事業内容 | ・先輩社員のメッセージ ・社員の一日 ・職場環境 | ・募集要項 ・採用スケジュール ・問い合わせフォーム |
ステップ4:カテゴライズしたページを階層構造に組み立てる
最後に、ページをカテゴリに従って階層構造に組み立てます。
階層が下になるごとにクリック数が増えるイメージを持つとわかりやすいでしょう。簡単に到達できないページは見落とされがちになるので、本当に必要な情報か精査しつつ、見てほしい情報を上位に配置させるのがおすすめです。
以上が基本的なサイト構成の作り方となります。
ホームページの各ページの基本構成

サイト構成は、ホームページの質を大きく左右することから、時間をかけてじっくりと検討することが大切です。とはいえ、中身を正確に理解していなければ、質の高いサイト構成を計画できません。
ここでは、3つの基本構成を見ていきましょう。
ファーストビュー
ファーストビューとは、ホームページを開いたときに、最初に表示される部分であり、ヘッダーやTOP画像、タイトルやキャッチフレーズが含まれるのが一般的です。
ページをスクロールせずに表示される画面であり、ファーストビューの質によってユーザーの離脱率が変わってきます。
メインコンテンツ
メインコンテンツはホームページの主軸になる部分であり、どのようなコンテンツを作るかを熟考する必要があります。たとえば、企業ホームページであれば、自社商品やサービスの紹介、ECサイトであれば商品情報などを掲載するのが一般的です。
クロージング・CTA
個人ブログの場合、単に情報を発信するだけなので、クロージングがなくても問題ありません。しかし、ホームページでは、目的に応じてクロージングやCTA(Call to Action)を作る必要があります。
そもそもクロージングやCTAとは、読者の背中を押すという解釈があり、ホームページの読者が、商品購入や資料請求したくなるような動線のことを指します。
ファーストビューで読者の興味をそそり、メインコンテンツでどのような商品やサービスがあるのか認知してもらう、さらにクロージングやCTAで問い合わせにつなげるといった構造が理想的なサイト構成といえるでしょう。
サイト構成を作成するときのポイント

質の高いサイト構成を作成することで、読者にとって有益な情報を発信でき、結果的にホームページの評価が上がったり、自社商品やサービスの問い合わせにつながったりします。
とはいえ、どうやってサイト作成すればいいのか、わからない方もいるでしょう。ここでは、押さえておきたいポイントを解説します。
競合サイトのホームページを参考にする
サイト構成を作成するときは、気になる競合サイトのホームページがどのようになっているかを確認し、参考にするのがおすすめです。同じ業種のホームページであれば、必要なコンテンツの構成もほとんど同じなので、参考にしやすいでしょう。
階層を深くしすぎない
ホームページの階層が深すぎると、読者が目的のページにたどり着くまでの時間と手間がかかってしまい、途中で離脱してしまう可能性が高まります。そのため、サイト設計時に、階層を深くしすぎないことを意識しましょう。
とはいえ、業種や業界によっては、内容が細かくどうしても下階層が必要になるケースも珍しくありません。下階層が必要な場合は、多くても3~4階層に留めておき、読者にとってわかりやすい動線づくりを意識しましょう。
1ページ1テーマにする
サイトを作るときは、可能な限り1ページ1テーマにしましょう。同じページ内に、異なるテーマが複数あると、読者にとって読みにくいページとなってしまい、離脱される可能性があります。
また、流し読みをしている読者にとっては、別のテーマが書かれていることで、目的のページではないと判断し、読むのをやめてしまうこともあるでしょう。
そのため、サイト構成を検討するときは、1ページ1テーマを意識することが大切です。
ユーザー目線で考える
ホームページを作るうえで、いろいろな情報を盛り込みたいと考える方もいるでしょう。しかし、情報が多すぎると、読者が目的のページを探しにくくなり、結果的に評価の低いホームページと判断されてしまうのです。
そのため、サイト構成段階でユーザー目線を意識して、読者ファーストのホームページ作成を心がけましょう。
まとめ
今回はサイト構成とは何か、作り方や基本の構成、ポイントなどを解説しました。
サイト構成はサイトの完成度や見やすさを左右する重要なポイントであり、サイト構成が作り込まれていなければ良質なホームページが完成しないばかりか、修正に手間やコストがかかる可能性があります。
ユーザー目線を意識しつつ、今回紹介した作り方やポイントを押さえて最適なサイト構成を検討してみてください。

記事の担当者(執筆/監修)
株式会社スマイクリエイト/代表取締役安部圭一/1972年5月 福岡県生まれ
・賃貸不動産経営管理士<登録番号(1)057435>
2019年5月にネット集客に特化したサッシ・ガラス屋ビジネスを創業。今まで蓄積した経験と知識を活かし、自身でキーワード選定やコンテンツ記事の執筆を行い、ローカルキーワード戦略に於いて、2000以上のキーワードで上位表示を達成する。その結果、新規お問い合わせは年間2,800件を超え、創業4年で年商1億円を突破。2023年よりネット集客の実績と経験を活かし再現性の高いSEOサポート事業を開始する。