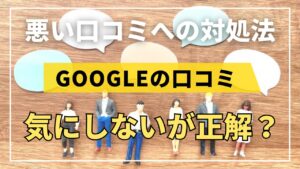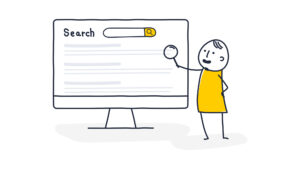さまざまな物やサービスが生まれている現代では、新たにビジネスを展開するときに必ずといっていいほど競合となる物やサービス、企業が存在します。
似たような商品やサービスに埋もれず、消費者に選んでもらうためには、自社のポジショニングや強みを明確にする必要があり、そのためは「競合分析」が欠かせません。
そこで今回は、競合分析の必要性や流れ、ポイントなどを解説します。「競合分析のやり方がわからない」という方はぜひ最後までご覧ください。
競合分析とは

競合分析とは、ライバルとなる商品やサービスの価格設定やラインナップ、機能のほか、他社のシェアなどを分析することであり、マーケティング戦略の基本となる重要なステップです。
なお、競合分析を行う対象は類似の商品・サービスを同じようなターゲットに販売する直接的な競合はもちろん、ターゲットが異なるものの似たような商品・サービスを展開していたり、代替品となる商品・サービスを販売していたりする間接的な競合も含まれます。
競合分析が必要な理由
新たに商品やサービスを販売したり、自社のシェアを拡大させたりするためには、競合分析が欠かせません。
では、なぜマーケティング戦略において競合分析が重要視されるのか、必要性を見ていきましょう。
独自の価値を見つけるため
物やサービスにあふれている現代では、新たにビジネスを展開しようとしても必ず競合が存在します。
消費者は数ある商品やサービスの選択肢の中から購入するものを選んでいるため、何らかの価値があると判断されなければ選んでもらえません。そこで競合分析を行い、他社の強みや弱みを把握し、自社だけの独自の価値を提供することが重要になります。
類似の商品やサービスがあっても、独自の価値を提供できていれば、消費者に選んでもらうことが可能になります。
新規のユーザーを獲得するため
競合分析は、新規のユーザーを獲得するのにも役立ちます。
他社の商品やサービスの分析を行うことで、まだ提供されていない領域、いわば「ブルーオーシャン」と呼ばれる販売領域を見つけられる可能性があるからです。たとえば、消費者が低価格で手軽なサービスを探しているのに対し、その領域では高価格帯のサービスしか展開されていなければ、ブルーオーシャンの領域となります。
ブルーオーシャンを見つけて顧客のニーズを満たす商品やサービスを提供できるようになれば、高いシェアを獲得できて企業成長につながるでしょう。
トレンドを押さえるため
顧客のニーズは日々変わっているため、一時的に売れた商品が売れ続けるとは限りません。そのため、物やサービスを継続的に売るためには、市場のトレンドを把握し、必要に応じてアップデートさせることが求められます。
競合分析では、他社の分析だけでなく、市場の動向や世間のトレンドも一緒に分析するため、世間のニーズも押さえた商品開発が実現可能になります。つまり、定期的な競合分析を通じてトレンドを知ることが商品を販売するうえで欠かせないといえるでしょう。
競合分析の3つの流れ

競合分析の必要性について理解できましたが、具体的にどのような流れで進めていくのでしょうか。
ここでは、競合分析を行うときの3つの流れを解説します。
1.目標を決める
まず、「何のために競合分析を行うのか」を明確にし、結果をもとに何を実現したいか目標を立てましょう。
たとえば、競合分析を通して他社の弱みを見つけたいのか、ブルーオーシャンの市場を見つけたいのかなどによって、アプローチの方法が変わります。目標を決めずに分析を始めてしまうと、手間やコストだけがかかってしまう可能性があるため、分析後の目標を決め奥ことが最初のステップとなります。
2.競合他社をリストアップする
目標を決めたら、競合となる企業を5~10社ほどピックアップします。
その際、取り扱う商品やターゲットが似ている会社を選ぶようにしましょう。競合の選定が進まないときは、検索エンジンやECサイトで自社の商品と同じカテゴリーのものを検索し、上位表示されたものを販売している会社を選ぶのがおすすめです。
3.テンプレートを活用する
調査対象の企業を選定したら、テンプレートを使って情報をまとめていきましょう。「競合他社 テンプレート」などのKWで検索すると、他社について調べるべき項目が一覧で表示されます。
実績や価格、ターゲット層などが主な項目ですが、テンプレートを使うと項目を一からピックアップする手間が省けるのでおすすめです。
以上のような流れて競合を調査し、目標に基づいてどのような戦略を立てるべきか戦略を立てていくことで、効率的な競合分析になるでしょう。
競合分析の2つのポイント

最後に、有益な競合分析を実現するために押さえておきたい2つのポイントを解説します。
先入観を持たずに競合分析する
自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分の先入観や仮設に合う情報ばかりを集めてしまうことを「確証バイアス」と言います。
競合分析を行う際、意識していなくても確証バイアスの効果によって、都合のよい情報ばかりを集めてしまうことも少なくありません。
せっかく他社を分析しているにもかかわらず、客観的な視点ではなく主観が優先されてしまっては、効果的な分析にならないため、先入観を捨てて、データや情報を冷静に分析するようにしましょう。
競合分析では新規参入もチェックする
競合分析を行うことは、マーケティングを成功させるうえで重要であることは確かですが、他社と比較することだけに集中してしまい、顧客が何を求めていくのかという意識が薄れがちです。とくに、新規顧客を獲得するにはどうすべきかという視点を忘れがちでしょう。
最終的に商品やサービスを購入するのは顧客であるため、自社の課題や他社を真似することばかりに集中せず、新規顧客に選んでもらえるかも検討しましょう。
まとめ
今回は、競合分析について解説しました。
競合分析は、他社と自社の商品やサービスを比較し、自社の強みや弱みを把握したり、新たな市場を発掘したりするのに役立つマーケティング戦略です。そのため、新たなビジネスを展開したり、すでにある商品やサービスを継続的に売り続けたりするうえで、欠かせないものだといえます。
ぜひ今回の記事を参考に、競合分析の必要性ややり方を押さえて、自社の商品開発などに生かしてください。
この記事を監修した人

記事の担当者(執筆/監修)
株式会社スマイクリエイト/代表取締役安部圭一/1972年5月 福岡県生まれ
・賃貸不動産経営管理士<登録番号(1)057435>
2019年5月にネット集客に特化したサッシ・ガラス屋ビジネスを創業。今まで蓄積した経験と知識を活かし、自身でキーワード選定やコンテンツ記事の執筆を行い、ローカルキーワード戦略に於いて、2000以上のキーワードで上位表示を達成する。その結果、新規お問い合わせは年間2,800件を超え、創業4年で年商1億円を突破。2023年よりネット集客の実績と経験を活かし再現性の高いSEOサポート事業を開始する。