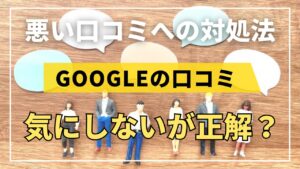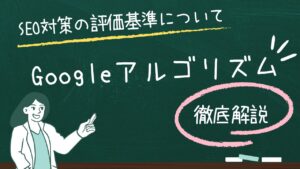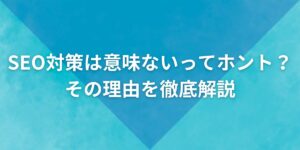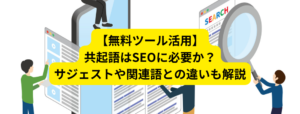検索エンジンでのキーワード検索した際、風評被害や誹謗中傷などに該当するページの検索順位を下げる手法に逆SEO対策があります。
しかし、対策を行う本人のサイトの評価が下がったり、倫理的に問題となったりするケースもあり、本当に実施すべきか慎重に判断しなければなりません。
そこで今回は、逆SEO対策とは何か、手法やリスクなどを解説します。
>北九州SEO対策会社|格安で確実な施策を全国の中小企業にお届けましすコンテンツ記事込で88,000円のみ!
逆SEO対策とは?
そもそも逆SEO対策とは、対象のサイトやコンテンツの検索順位を下げるために行う施策のことを指します。
通常、SEO対策といえば、自社サイトなどを上位表示させるために行う取り組みのことを指しますが、反対に、あえて表示順位を下げようとする行為を“逆”SEO対策と言うのです。
逆SEO対策の目的
「なぜそのようなことをするの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。目的は、誹謗中傷やデマの拡散など、悪質な風評被害への対策です。
たとえば、企業名を検索したときに、検索上位にデマ情報や悪質な口コミが書かれているコンテンツが表示されると、ユーザーが企業に対して不信感を持ったり、購買意欲が低下したりしてしまうかもしれません。
そこで、企業価値やブランディングを維持するために、該当のサイトの検索順位を落とし、ユーザーが情報を目にしないようにするのです。
逆SEO対策の手法4選

では、具体的にどのような手法で対策を行うのか見ていきましょう。
手法1:サイトを複数作成して検索順位を上げる
Googleなどの検索エンジンでは、他サイトとの相対評価で検索順位が決まります。
そのため、検索エンジンから評価を受けやすいサイトを複数作成し、狙ったキーワードで上位表示させることによって、結果的に該当サイトの検索順位を下げられます。
手法2:検索上位をキープする
手法1の方法で効果が出て、作成したサイトが上位表示されるようになったら、常に検索順位をキープできるようにしましょう。
順位を定期的にチェックし、情報を更新したり、良質なコンテンツを増やしたりすると、検索順位をキープしやすくなります。ただし、Googleには200以上のアルゴリズムがあり、定期的に改変が加えられているため、常に上位をキープし続けるのは用意ではありません。
手法3:コンテンツの削除を依頼する
原因となるコンテンツを削除してもらうことも対策の一つです。
サイトやコンテンツの運営者に直接連絡し、削除依頼をしましょう。ただし、感情的になるのではなく、客観的視点や根拠をもとに削除をお願いすることが大切です。ただし、運営元が削除に応じない場合、弁護士に相談するなど別の対策を考えなければなりません。
また、法律違反や権利の侵害に該当しているサイトである場合、Googleに削除依頼を出すことも可能です。
グレーな手法1:コピーサイトを複数作成する
Googleのアルゴリズムとして、類似したコンテンツはスパムと見なすというものがあります。そこで、該当サイトの類似サイトを複数作成し、該当サイトの評価を下げて検索順位を落とすという手法もあります。
ただし、許可なくサイトを複製することは著作権侵害にあたるため、リスクのある方法であると認識しておきましょう。
グレーな手法2:低品質な被リンクを送る
該当サイトの評価を下げるために、低品質な被リンクを大量に送り検索順位を落とす手法もあります。
検索エンジンから高い評価を受けるサイトを作成するためには、質の高いサイトから被リンクを自然発生的に受けることが重要となります。
そこで、対象サイトに対して、大量の低品質なサイトの被リンクを意図的に送ることで検索エンジンからの評価が下がりやすくなるのです。
ただし、こちらの手法はスパム行為にあたるため、原則行うべきではありません。自社サイトが同様の被害に遭わないために知っておくようにしましょう。
逆SEO対策の注意点・リスク

悪質なサイトの行為に悩んでいる場合でも、本当に施策を実施するべきか慎重に判断しなければなりません。
ここでは、注意点やリスクについて解説します。
効果が出るまでに時間がかかる
逆SEO対策を実施しても、すぐに効果が出るわけではないことが注意点として挙げられます。
検索エンジンでは、サイトの評価によって表示順位を変えているとはいえ、短期間のうちに検索順位が大きく変わることは稀です。
そのため、施策を行っても、数ヶ月は検索順位が変わらない可能性があります。短期的な対策を検討する場合は、サイトの運営者に削除依頼を行うのがおすすめです。ただし、削除依頼に応じない場合は、解決まで時間がかかるケースもあるでしょう。
倫理的・モラル的にマナー違反となる可能性がある
悪質なサイトであっても、結果的に検索エンジンから評価されて上位表示されていることに変わりはありません。
そのため、あえて対象サイトの検索順位を下げようとする行為は、倫理的・モラル的にマナー違反となる可能性があります。
検索エンジンからペナルティを受ける場合がある
逆SEO対策の手法によっては、相手のサイトやコンテンツに対してスパムにあたる行為をすることになります。
そのため、対策をしている本人のサイト・コンテンツの評価が下がったり、法的罰則を受けたりする可能性もあります。逆SEO対策は、手法によっては対策する本人にもリスクを伴うことを認識しておきましょう。
まとめ
今回は、逆SEO対策について解説しました。
逆SEO対策とは、対象サイトやコンテンツの検索順位を下げる行為を指します。デマ情報や悪質な口コミなどを記載し、企業や商品に対して風評被害を与えるようなコンテンツに対して行われるのが基本です。
ただ、さまざまな手法があり、なかにはモラル違反になったり、スパム行為に該当したりするようなグレーな方法もあります。そのため、リスクについても認識したうえで対策方法を検討しましょう。

記事の担当者(執筆/監修)
株式会社スマイクリエイト/代表取締役安部圭一/1972年5月 福岡県生まれ
・賃貸不動産経営管理士<登録番号(1)057435>
2019年5月にネット集客に特化したサッシ・ガラス屋ビジネスを創業。今まで蓄積した経験と知識を活かし、自身でキーワード選定やコンテンツ記事の執筆を行い、ローカルキーワード戦略に於いて、2000以上のキーワードで上位表示を達成する。その結果、新規お問い合わせは年間2,800件を超え、創業4年で年商1億円を突破。2023年よりネット集客の実績と経験を活かし再現性の高いSEOサポート事業を開始する。